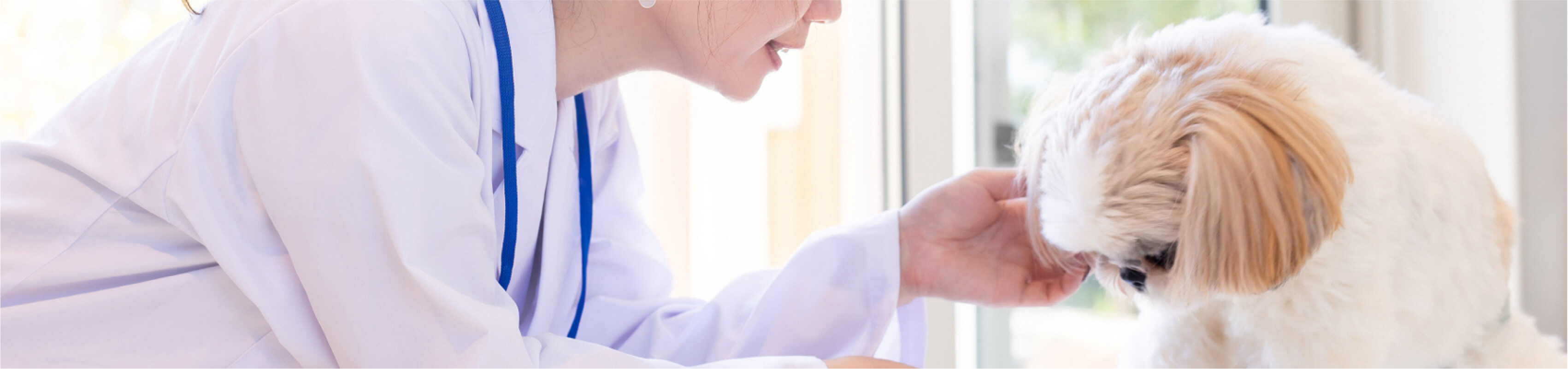

 循環器科
循環器科
僧帽弁閉鎖不全症
犬の心臓病の中で最も遭遇する機会の多い病態です。心臓の左側に存在する僧帽弁と呼ばれる逆流防止弁が変形することにより、血液の逆流が生じる病態です。心臓の聴診を行い、心臓の収縮期に雑音が生じていることによって、気づくケースが多いです。
軽度な状態であれば、犬自身も無症状なため変化が確認されませんが、病態の進行とともに発咳、運動不耐性などの症状が発現し、重症化すると肺水腫と呼ばれる肺に水が溜まる病態に進行し、呼吸困難を引き起こすことで命に関わる可能性があります。
診断をするには胸部レントゲン検査、心臓エコー検査により判断します。
胸部レントゲン検査により、心臓全体のサイズと心臓周囲の血管、肺と肺血管の状態を確認します。
心臓エコー検査により、心臓内の逆流の存在部位、心拡大の有無、心臓収縮力、逆流速度の測定、左心房から左心室への血液流入速度(E波,A波)の測定などを行います。多くはありませんが、心臓腫瘍、心筋炎、心内膜炎などの心臓病以外の原因による二次的な心臓病も見られることがあるため、心臓全体の構造確認も同時に行います。
僧帽弁閉鎖不全症は左心疾患であるため、僧帽弁における逆流と左心拡大を特徴としますが、病態の進行により右心への負荷も高まると三尖弁逆流が生じ、右心拡大につながることもあります。さらに肺動脈弁の逆流も生じると肺高血圧症の可能性も考慮する必要性があり病態としてより複雑になるため、安定化するまでは複数回の心臓エコー検査が必要になることが多いです。
心臓病の治療で大事なことは、病院での画像診断結果以外にも自宅での呼吸状態や運動能力が安定しているかもポイントになります。
心臓病が進行した際には最初に発咳がひどくなるケースが多いため、この変化にいかにはやく気づき、治療に繋げるかが重要と考えます。
心臓病があったとしても、軽度かつ安定化している場合においては、数ヶ月ごとの心臓チェックでほとんど通常の生活が可能ですので、もし心臓病が疑われた際には早めの心臓検査行い「今の心臓の状態」をしっかり把握することを推奨いたします。
